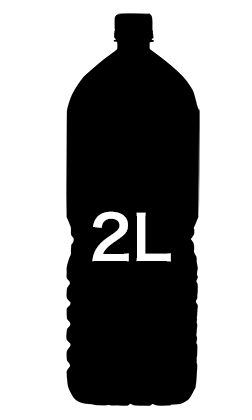駒ノ湯から越後駒ヶ岳へ
国道から駒ノ湯へと入り、狭い道を行き止まりまで進むと登山口に突き当たる。
左側には10台ほどの車が停められる。
アブが・・・
季節のせいかアブがとても多く車のドアを開けた瞬間に車内へと大量のアブが飛び込み、登山準備中も手足に次々と止まり噛みつこうとしてくる。
道路の横にある登山カードのポストが建てられたところが登山口で、とても小さく主だった目印もないため分かりづらい。
先を覗き込みながら、登山道に従って緑の中へと入っていくとすぐに20mほどの吊り橋が架かっていた。
1mほどの幅で歩く度に揺れ、手すり代わりのワイヤには転落防止ネットが張られている。
吊り橋を渡ると右へ左へと折れた後すぐに急登が始まる。
尾根に沿って登っていく駒ノ湯からの登山道は、急な斜面を直登していくようなルートで、急斜面によくあるような九十九折りにはなっていない。
まっすぐに続く尾根の急斜面を登っていく。
雨の降った後は登山道は足元が緩く、水たまりもところどころに。
とにかく直登な感じ
20分ほど登ると右側の木々の合間から山頂部が見える。
左右に見える景色を楽しみながら3mほどの幅の尾根道を緩やかに登り、急登と緩斜面を繰り返していく。
ところどころで景色が開けると、奥只見の山々が深く聳え並んでいるのが見える。
急登と緩斜面を繰り返しながら標高1000mを越え、中間地点の小倉山が近く高く見え始めると、このルートの核心部に入っていく。
あれかー・・・
日の照りつける急登の尾根を真っ直ぐに登っていく。
周囲の山々を見渡す余裕も無く急登を登る。
唯一の鎖場だった濡れた岩の急登を過ぎ、いったん斜面が緩み崩れた斜面をトラバースして再び急登へと入っていく。
登山口から1時間55分掛けて小倉山に到着。
周囲を草木に囲まれたピークで、東側の展望が良く荒沢岳がよく見える。
登山道はそのまま先へと続き、小倉山から2分ほど下りると枝折峠からの登山道と合流した。
合流地点は登山道も広く草の背も低かったため、小倉山の山頂と同じように左側には荒沢岳が見え眺望が良かった。
先へと続く登山道を見ると越後駒ヶ岳が大きく高く見えた。
ここまでの急登は辛かった
合流地点からの登山道は、小倉山までの急登から変わって緩やかに登りながら長く続いている。
トンネルのように枝を伸ばした中を潜り、整備された木段を登りながら標高を上げていく。
このあたりからちょうど太陽を背にするようにして登っていくので、日光を直接浴びるような形になり、体感温度はとても高い。
風が吹けば涼しさも感じるだろうところも、樹林帯に覆われているためか風もなく、なかなかに我慢の登り坂だった。
そういえばアブがいなくなってる
小倉山の分岐から30分ほど歩いて百草ノ池を過ぎた。
湿原と呼ぶには小さな池塘がポツンと見えるだけで、そう広くはない湿地が笹に囲まれていた。
百草ノ池ってもっと大きいと思ってた
越後駒ヶ岳の山頂もかなり近づいて見え、山頂までに目の前のピークを越える必要がある様子が見てとれた。
ピークへの急斜面に取り付くと、周りにあった背の高い植物も徐々に減り始め、足元の土は岩々とした様相に変わっていく。
周りを見渡すと越後三山の中ノ岳の存在感があり、尾瀬の山並みも見通すことができる。
折り重なる山々の眺めは良い
山頂の下には駒ノ小屋のアンテナらしき鉄棒が建っているのが見え、高く見える場所も視界から感じるよりも近くまでやってきたように感じた。
左右を笹に囲まれた岩の急登を登って駒ノ小屋へと近づいて行く。
小さな段差が連続しているような岩の登山道も、崩れづらくシッカリしているために登山靴のグリップが効いて歩きやすい。
登山口から3時間が経ったくらいの時間で駒ノ小屋に到着。
小屋の前に流しっぱなしになっている水を頂き、間近にまでやってきた山頂を目指す。
若干、緩やかに変わった登山道の木段を踏み、駒ノ小屋から10分ほどで稜線上の中ノ岳への分岐点に到着した。
稜線上の緩やかな斜面を山頂へ。
ここの水が美味かった
着いた
越後駒ヶ岳山頂
駒ノ湯登山口から3時間23分、越後駒ヶ岳の山頂に到着した。
10mほどの円形の山頂はベンチが周囲に置かれ、八海山を背にして像が祀られていた。
雲が多い中でも周囲への展望は良く、八海山との間の深く落ち込んだ谷、その先の八海山の八峰と中ノ岳とを繋ぐ険しい稜線が見えた。
魚沼の市街地を見下ろし、山深い奥只見と険しくもカッコの良い魚沼の山々を見渡す山頂からの眺望はとても良く、時間と天候が許すのなら長く眺めていたいところだった。
大変だった
越後駒ヶ岳からの下山
下山は登りと同じ駒ノ湯への急斜面を下りる。
駒ノ小屋へと戻り、空へ飛び出すような眺めから樹林帯へと戻っていく。
蒸し暑い空気の篭もるから振り返ると、あっという間に山頂が遠く離れていく。
小倉山の分岐へと戻ると、ここからはより深く樹林帯に覆われた登山道へと戻り眺望も変わる。
登りで苦労した急な斜面は下りでも同じで、滑りやすく湿った土質と木の根にバランスを保ちながら歩いていく。
斜面は急勾配でもなかなかに標高は下がらず、長く感じる下り坂で、標高を下げるほどに暑く蒸した空気が流れる。
尾根のすぐ下に駒ノ湯旅館の屋根が見えた瞬間には安堵した。
またアブの中へ戻ってく