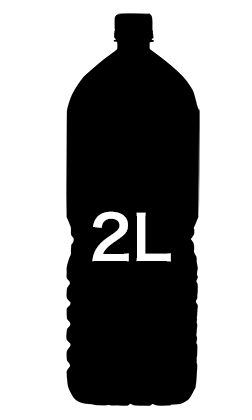二荒山神社から男体山へ
中禅寺湖の北側、二荒山神社中宮祠から男体山へ登ることができる。
駐車場は多く設けられており、二荒山神社の鳥居の前に南駐車場。
鳥居から社地に入ると2箇所の駐車場がある。
男体山は二荒山神社の御神体であるため、山へ入るには神社の許可が必要になる。
車を停めて準備を整えた後、門を潜ってすぐ横にある社務所へ。
ここで入山料500円を払うと初めての登山者には登山道の説明があり、簡単な地図と交通安全のお守りがもらえる。
ごくごく簡単な説明ではあるけれど、山頂までの目安となる時間や鳥居を潜ることなどの注意点も聞くことができる。
登山口は拝殿の横にある鳥居から。
二荒山神社では「登山」ではなく御神体を拝むための「登拝」という呼び名を使っている。
鳥居と門を潜ると先には石段が続いていく。
上へと続く石段を上ると木段に変わり緩やかに上へ上へと登っていく。
5分ほど登ったところで遙拝所が建っていた。
遙拝所は御嶽山や沖ノ島など離れたところから御神体を拝む際に使用されている。
遙拝所のすぐ上には一合目の石碑と鳥居が立てられていた。
ここから登山道の勾配はキツさを増し、笹に囲まれたやわらかな土の上をグイグイと登っていく。
段差も少なく、ただただ急な斜面を登っていく。
20分ほどで車道に出た。ここから折り返しながら4合目の鳥居まで歩いて行く。
ここまで急斜面だった分、車道は緩く歩きやすく登っていくことができる。
4合目からの登山道
男体山4合目の鳥居から本格的な登山道へと入っていく。
笹とやわらかな土の感触は1合目と同じ。
湿気を含むと滑りやすそうな土質で折り返しながら少しずつ高度を上げていく。
ところどころに段差があり、木で整備されているところも多い。
5合目には4合目から15分足らず。
小さな小屋が建っており、中では休憩を取ることができる。
5合目からの九十九折りの斜面は木が開けているところもあり、中禅寺湖を見下ろすこともできる。
10分ほど登ったところで6合目を通過。
大きな岩も目立ち、ガレガレとした雰囲気でちょうど広く開いているので麓を見下ろすことができる。
6合目のガレ場の雰囲気はその場だけで、石碑を過ぎると再び樹林帯に入っていく。
足元には木の根が張った湿った土。
葉に覆われて薄暗く大きな石は土に埋まっている。
樹林帯はすぐに過ぎて、再び開けたガレ場が上へと続いていく。
石の上を渡るように登っていくと7合目の小屋が見えた。
6合目と7合目は20分ほど。
周りを覆っていた木は、まだ葉が茂る前のような状態で、登る先が明るい。
さらに15分ほど登ったところで金属製の鳥居を潜って行く。
この鳥居のすぐ上には8合目があり、瀧尾神社の小さな祠が祀られている。
横には鎖が垂れており登山道上ではないので使用しないが、どこに続いていくのか気になる。
8合目を過ぎて5分と経たないうちに、勾配は緩く代わりガレ場も樹林帯に戻った。
それまで急勾配を登ってきた足腰がここで癒されるよう。
それも僅かな区間で、徐々に勾配がきつく戻っていき、滑りやすそうな勾配を登っていくと9合目に到着。
9合目を過ぎると木の向こうに山頂らしき影が見えてくる。
よくあるもので山頂だと思っていたピークが実際にはその向こうが山頂だったということも。
ここでぬか喜びはしないと思い、あそこまでいけば山頂が見えるいうつもりで勾配を登っていく。
樹林帯の終わりは突然だった。進む先の周りを覆っていた木が一気に後方へ下がり、周りには熔岩石の赤い地面ばかり。
崩れやすい砂礫の足元に、階高の高い木段が並べられ、それを避けるように踏み跡が伸びている。
晴れていればここから中禅寺湖や戦場ヶ原を見下ろしながらの登山になるはずが、今回はあいにくのガスで周囲が見えないどころか山頂も見えない。
高度を上げていくほどに土は赤くなり熔岩石ばかりの周囲。
ただひたすらに登り、山頂の鳥居が見えたのは突然だった。
男体山山頂
登山口から2時間8分ほど。男体山の山頂にある鳥居を潜った。
鳥居の正面には二荒山神社の奥宮。
左側には二荒山大御神の銅像が中禅寺湖を見下ろすように建っている。
山頂部分は広く、最も標高が高い三角点はさらに東側に進んだ小高い石の上にある。
鳥居と石碑が置かれた先に刀を象ったような金属製のモニュメント。
男体山のシンボル的なもので、ここで記念写真を撮る人も多い。
真っ白な中、かろうじて戦場ヶ原を見下ろすことができた。
下山路
山頂からは志津乗越を経由して戦場ヶ原へと下りることのできるルートが続いているが、今回は二荒山神社へのピストン。
登ってきた登山道を下りていく。
急登のガレ場は足の踏み場を選びながら。
山頂を覆っていたガスは、やはり下山でも6合目付近まで晴れることはなく、中禅寺湖を見下ろしながらの下山ができたのは僅かだった。