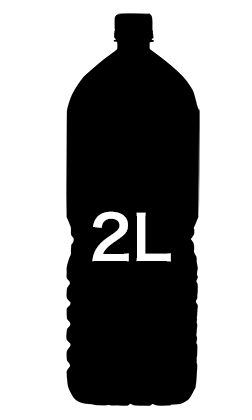真田氏の城跡の残る岩櫃山へ
岩櫃城の跡から近く、見物者の多い一本松登山口。
入口にある小さな休憩所では、登山道や周辺の温泉情報なども厚く取り揃えられている。
軽装の城趾見物者に混じって岩櫃山への登山道へと入っていく。
城跡を経由するルートと、まっすぐに山頂へと続くルートの分岐や、尾根通りと沢通りの分岐など、歩くことのできる場所が様々なのがこの登山口。
今回は山頂へと近いルートで登っていく。
登山口から5分と経たないほどで差し掛かった尾根通りと沢渡通りの分岐を右へ。
石が多く転がり、岩壁を見上げながら歩く沢通りへ。
たくさんの石が転がっているとはいっても歩くべき場所は整備されているため歩くことは難しくなく、落ち葉の積もった足元は柔らかい。
緩やかな坂道を徐々に登っていくと次第に岩壁に囲まれるようになった。
登山口から15分ほどで尾根通りと合流し、天狗の蹴上げ岩という大きな岩のハシゴを登る。
左右は切り立った岩で、その表面が青く見える。
岩の間を縫うように進んでいくと、いよいよ山頂の稜線が枝の間から透けて見えてくる。
稜線までの斜面を九十九折りに登り、8合目という看板が立てられた尾根へ。
斜面をトラバースするように登ると、山頂を見渡すことのできる巨岩のピークに出た。
山頂に取り付いている先行者が鎖場で難航している様子を見ながら、ここで登るタイミングを計る。
鎖と梯子を伝って岩のピークを下り、狭い尾根から山頂の取り付きへ。
このルートでの最大の難所になる最後の鎖場へ。
まっすぐに垂らされた鎖を掴み、窪みと出っ張りを確認しながら山頂へと登る。
岩櫃山山頂
一本松登山口からスタートして32分。岩櫃山山頂へ到着した。
10人ほどが滞在できる程度の広さで、周囲が崖になっているために高度感のある山頂。
一番高い部分からは、真下に郷原の集落が見える。
周りの山を見渡すと浅間山や谷川岳、日光白根山などの有名な山々が見える。
ぐるりと鎖が張られた物々しい雰囲気とは違った景色が楽しめた。
岩櫃山からの下山路
山頂の鎖場を下り、下山のルートは赤岩通りへ。
再び岩のピークを越えて岩壁の間を縫う登山道を下りていく。沢通りと尾根通りの分岐を尾根通りへ。するとすぐに赤岩通りの分岐があり、それを右へと進む。
いくつも分岐が続くルートになるが、その度に看板が立てられているので迷うことはない。十二様通りとの分岐を過ぎると、穏やかだった勾配は一気に急に変わる。
鎖が垂らされ、赤岩通りという名前の通りの赤い岩肌。小石が滑りやすい赤い斜面を下りて、一気に高度を下げていく。
階段が整備されているものの勾配はあるので、登りに選んだときの苦労が思いやられる。
赤岩通りの下山時間は25分ほど。岩櫃山を登り始めた一本松登山口の反対側に下りた。