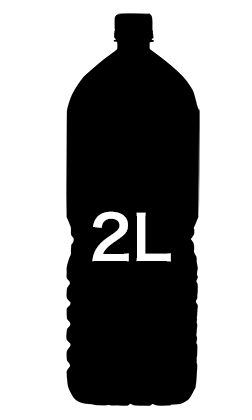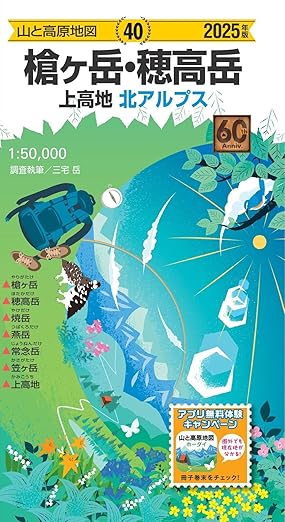中ノ湯から焼岳へ
焼岳への最寄りルートになる新中ノ湯ルートは、安房峠へ中ノ湯温泉を過ぎてさらに上に登ったところに登山口がある。
登山口のある道路の横は広く開いているので、車が何台か停められる。
焼岳への登山道に入ると、入口に大きな雪の塊が残っていた。
雪を避けるように登山道を進んでいく。
序盤は緩やかな登り坂で、周りには緑に囲まれている。
登山口から5分ほど進んだところで九十九折りに変わり、ここから急勾配の登山道が続く。
足元には木の根がはっているので、足を掛けたり跨いだりしながら登っていく。
湿度が高いためか虫が多く、歩いていると後ろをついてきて立ち止まると顔の周りを飛び交う。
この虫に噛まれると腫れが引くまで数日かかるので注意。
登山口から40分ほど。木の間から焼岳が見えた。
その稜線からは蒸気が上がっているのも見える。
焼岳が見えると急勾配だった登山道は緩やかに変わる。
少し歩くと周りを囲んでいた木も開けて隙間から見えていた焼岳の全体像が見渡せた。
向こうには穂高岳。
晴れた日には気持ちの良い登山道だった。
焼岳山頂へのガレ場
焼岳を見上げ穂高岳を見晴ながら進むと、山頂への登り坂が始まる。
足元には木段が整備され登りやすくなっているものの、周りに木が無くなっているので陽が当たり暑い。
土だった足元は徐々にガレ場に変わっていく。
目指す稜線には蒸気が噴き出しているのが見える。
10mほど残った雪渓を渡りしばらく登ると、岩に大きく2300mと書かれた印があった。
ガレ場の坂道を登ること40分。
ようやく北峰と南峰の鞍部に到着。
火山湖がすぐ近くに見え、遠く雪の積もった笠ヶ岳が見えた。
鞍部を右に曲がって北峰へ。
斜面をトラバースするように北峰の直下を横切っていく。
噴き出している蒸気は硫黄の匂いが強く、息が上がった状態にはこのガスが息苦しい。
斜面を横切って急なガレ場を登ると、焼岳小屋方面への分岐点に到着した。
焼岳山頂へ
分岐点からは穂高岳の全体が大きく見え、その先には槍ヶ岳、裏銀座の稜線や笠ヶ岳が見渡せた。
登山ルートは左へ曲がって山頂を巻くように登っていく。
焼岳山頂近くのガレ場がこのルートの核心部で、危険箇所の少ない中で注意が必要な場所になっている。
段差の高い岩場で、右側を見ると高度感のある斜面。
十分に気をつけながら岩場を上がると、山頂に立つ標が見えた。
焼岳に到着
中ノ湯登山口から2時間。
焼岳山頂に到着した。
山頂では真下から蒸気が上がってくるため、場所を選んで景色を楽しむ。
北側には上高地を見下ろして穂高岳。東側には霞沢岳。
西側には笠ヶ岳。
新穂高温泉も見下ろすことができた。
登山道から悩まされた虫は山頂でも飛び交っていたため、焼岳では虫除けを携帯するのも良さそう。