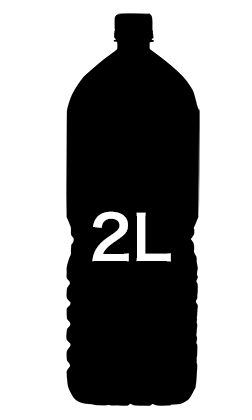四阿山へ菅平から
根子岳へ縦走
四阿山の北側に位置する須坂市から菅平高原へ向かって県道34号線の大笹街道を上がっていく。
市街地からは30分ほど。
奥ダボススノーパーク方面から菅平牧場へと向かう
菅平から登るには高原管理事務所で通行料金を払う。
道沿いの菅平高原管理事務所に停まったところ、まったくの無人で、11月は通行料金の徴収がされないようだった。
駐車場に車を停め、準備を整えて8時頃スタート。
牧場を横目に登山口へ進み、柵の横を過ぎ、小さな沢を越え、だんだんと笹が茂る山の中へ入っていく。
足元は霜が降りて硬く締まっている。
湿気てドロドロになっているより歩きやすい。
勾配は割と急。
紅葉も終わり、落ち葉の季節になったので眺望も良い。
菅平は北信と東信の間にあるので、地形的に両方が望める。
長野市と須坂市と、北は遠く妙高山もよく見え、浅間山の東側がよく見える。
30分ほど登り進み、目安になる小四阿へ。
隣にある根子岳はほぼ同じ高さに見える。四阿山もだいぶ近くに見えてきた。
風の強い四阿山山頂へ
足元はだんだんと岩の転がる道になってきて、標高の高い山らしくなってきた。
木が無くなった分、風が強く当たって寒い。
小さなピークの上って下りることを繰り返し、後ろを振り向くと北アルプスと菅平の平地がよく見える。
そして生えている木は、ちょうど西側だけ雪が解けずに凍みている。
頂上が近くなると、とってもキレイな階段が敷かれていた。
ところどころ踏み板が外れてはいたけれど、この高さまで来て、この整備され具合は驚いた。
登山道での階段は自分の歩幅で歩けないのでとても疲労する。
頂上までもうひと息というところでのこの用意は「なぜ?」と思う。
四阿山には南峰と北峰がある。
ほとんど標高に違いは無いのだけれど、どちらも小さな社が設けてある。
群馬から登ると先に見える北峰。
西側に石積みがあるのは、やはり風対策なのだろうか。
登山口からここまで約2時間ほど。
頂上の標はふたつ立っていた。
いつものように写真を撮って、少しでも風の避けられるところに腰を掛けた。
コーヒーを入れようと火を付けるとガスコンロの下が凍り付いてしまう。
気化熱をそのまま地面に伝えているのと、風が強いのと、もともと凍みていたのとで、とっても凍りやすい条件が整っていたのだろう。
蹴飛ばしてもコンロは動かないので沸いたお湯を掛けて外す。
西側にある根子岳。
群馬の方は、草津白根山や横手もよく見える。こちらがわのルートは、本当に尾根を伝ってくるようだ。
標高差はそんなにないらしい。須坂方面を眺めると、妙高がとてもよく見える。
妙高の後ろは火打山だろうか。
つい先ほど登ってきた登山道は、西側がしっかりと凍り付いているのが見えた。
この場所も冬は風が冷たくて厳しいところなのだろう。こうやって菅平を見ると、今の季節は落葉松の紅葉がちょうど良い。
下山ルート根子岳を経由することに
このルートはとにかく勾配が急で、長い道では無いのだけれど雪が残っているために滑る。
足元に細心の注意を払って転ばないように。
下りきると視界が広がり、一面の笹。
もふもふとしているような質感の先に根子岳が見える。
このルートも風を避けてくれる木々が無くて、とにかく強く風が当たる。
気温も上がってきたようで、登りでは凍みていた登山道も、ここではドロドロになってきた。
強い風とドロドロで滑る道。これは予想外に気を遣う。
帽子が飛ばされそうで、足の裏には土がごっそり。
そんな目の前には、大きな岩がいくつか点在している。
きっとこれは白根山の噴火の時にここまで飛んできたのでは無かろうか。
石の間を抜け、強い風の中、頂上に到着。振り向けば、さっき登ってきた四阿山が見える。
四阿山からここまで1時間ほど。
ここも風を避けるところが無くて寒い。
四阿山ほどではないけれど、眺望が良くて、北側の林がキレイだった。
根子岳からの帰りは、比較的緩やかな傾斜が続く。
笹だらけの道から、木に囲まれた道に変わり、駐車場に到着。
この下山ルートは約30分ほど。