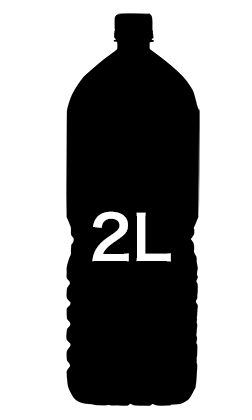急登の子檀嶺岳村松西洞
上田市から西へ向かい修那羅峠方面へ。
麻績村へと繋がる国道の道中で青木村が広がる。
女神岳や大明神岳といった端整な三角錐の里山と、青木村の南に見える独鈷山の荒々しい岩峰群、その反対側には子檀嶺岳。
青木村の道の駅近く、村役場の横から村松地区の急な坂道を上っていくとゲートがあり、その横に数台の車が停められるスペースがあった。
準備を整えてゲートを開ける。
しばらくは林道を登っていくのが子檀嶺岳らしくて良い。
子檀嶺岳のあちこちにある林道の地図が欲しい
アスファルトの上にはうっすらと雪が乗り、木陰では固く凍っていた。
滑りやすい足元に気をつけながら進んで行くと陽当たりが良くなり、バリバリと音を立てていた道路は、泥濘んで滑りやすく変わる。
アスファルトはいつの間にか終わって、大きな窪みや溝が目立つ林道になっていた。
林業のための大型車や重機なら、この窪みも難なく通過していくのだろう。
いつかこの林道がどこへ繋がっているのかを確かめてみたい。
林道の左右には「止山」と書かれた貼り紙が目立つ。
きっとこのあたりの山と同じように茸が生えるのだろうと想像をしながら、なんとなく気まずく感じつつ林道を進んで行く。
決められた登山道以外に立ち入るつもりもないので、後ろめたく思うこともないのだけれど。
このあたりは茸山が多くて、あちこちで見る気がする
10分ほど登ったところ
10分ほど登ったところで山頂を指す看板が建っていた。
ここが本来の登山口らしい。
丸太を括り付けた橋を渡ると、斜面を横切りながらの登り坂が続いていく。
序盤からなかなかの急登で、山の形状から覚悟はしていたものの、やはり序盤からの急登は堪える。
雪や凍みたところもなく、ソールに感じる落ち葉の柔らかさが登りやすい。
ただ角度が緩まる気配はなさそうで、急斜面を横切ったり、右へ左へと折り返して登山道が続いて行く。
木々が厚いため周りに見える景色はなく、黙々と斜面を登り、ゲートから30分ほど経ったところで正面に山頂部が見えた。
麓の街から見えた岩壁が近い。
右側には当郷管社コースと思われる尾根が見えた。
眺めが良いと気分が晴れる
登山道の日影には乾いた雪が目立ち、場所によっては凍結している雰囲気に変わった。
岩壁を間近に見てから5分ほどで、急登から緩斜面に変わった。
南側にある湯坂山と子檀嶺岳を繋ぐ尾根に出たようで、この地点で標高は約980m。
緩やかな尾根の先にはさらに急な斜面が見える。
穏やかな呼吸で歩けるのは、ほんの僅かなようだった。
なだらかだと思った瞬間に、すぐそこに急登が見えるヤツ
それまで葉の付いた木々の間を縫って登ってきたのが、尾根に出ると急に葉の落ちた木々に変わり、一気に陽当たりが良くなる。
日影で雪が残り凍っていた様子は一変した。
ここまでの単調な急登も、段差が高く、石を踏むような斜面に変わって、まったく別の山に来たような雰囲気の変わりようだった。
ゲートから40分
右側には岩壁。
これがきっと仏岩なのだろうと、それらしく見える角度があるのだろうかと、チラチラと見ながら登る。
木の根を踏み、岩の段差を越えると、仏岩を指す看板が建っていた。
近づくなと書かれてはいるものの、明かな踏み跡と、矢印に惹かれて仏岩の方向へと進む。
ただ垂直に近い岩壁の上を歩くことは、見るからに分かっていたので、看板の通りに近づきすぎないように気をつけた。
眺めの良い場所で仏岩を見下ろすものの、期待したほど、それらしい形には見えなかった。
仏といえば仏に見えないこともない
すぐに元の登山道と合流し、さらに登りは急斜面になっていく。
このあたりでは落ち葉が乾いて、まるで氷の上に足を乗せているように滑る。
しっかりと踏み込まないと、乗せた足が落ち葉ごと下へと流れてしまうようで、段差がある方がどれだけ楽かと感じた。
もし転倒しようものなら、滑ったままどこまでも落ちていきそうな斜面。
九十九折りであることが安心で、直登するようなところは、手に持ったストックをしっかりと突いた。
滑って危ない
仏岩から10分
仏岩から10分ほどで眺めの良い場所に出た。
尾根の右側が深く切れ落ちた場所で、眺めが良いということは、木々がなく捕まることができない場所。
あいかわらず落ち葉は滑りやすく、足を停めれば眺めを楽しむ余裕はあるものの、歩き出したら転ばないようにと気を配る。
ただ、東側に見える上田市街と遠くの浅間山外輪山、西側の北アルプスと四阿屋山までに折り重なる山波がキレイだった。
まったく雰囲気の違う景色を楽しめる尾根は、滑りやすい緊張感を充分に和ませてくれた。
山頂は近い。
滑る
先を見ると尾根らしい地形と木々の向こうが明るく見える。
田沢嶺浦コースとの合流地点が近い。
合流すれば山頂はすぐ。
葉っぱの下は凍ってそう
想像以上の滑りやすさで、山頂に着けるのかと緊張感が高まっていたところに少し安心感が持てた。
葉の無かった木々から、また葉を付けた木々の間を歩くように変わったため、日影ができて雪が残っている。
しかも標高が上がったぶんだけ、凍みているところも多い。
登りよりも下りで難儀しそうだった。
ゲートから1時間
ゲートから1時間を過ぎたころ、山頂から繋がる尾根に出た。
田沢嶺浦コースとの合流地点から尾根を少し登り、登り切って平坦になったあと少し下ると山頂に建つ社殿が見えた。
尾根の上は風が冷たくて
子檀嶺岳山頂
ゲートから1時間4分
ゲートから1時間4分で子檀嶺岳の山頂に到着した。
ふたつの社殿と祠が南に向けて1基置かれている。
遠くには蓼科山が見え、手前には独鈷山や女神岳と夫神岳。
雲が多いながらも良く晴れているおかげで上田から南側の眺めが良い。
山頂の北側は木々が茂り南側ほどの眺望はないものの、間近には聖山が見える。
雪雲が厚いために北アルプスは白く見ることができなかった。
無事に登ってこられて良かった
下山
下山は登りと同じ村松へのピストンだった。
山頂から数分の尾根上は風が吹き冷たく指先が痛む。
分岐から南向きの斜面へと下りて風から逃れることはできたものの、登りで苦労した急勾配と落ち葉の滑りやすさは、下りで怖さを感じるほどだった。
気を抜くと尻餅を突いて滑り落ちそうで気が気ではなかった。
登りより下りの方が怖い
葉の無い木々が並ぶ一帯は特に落ち葉が厚く、ソールを蹴り込むようなこともできない。
視界を遮る葉がないので眺めが良いものの、尾根横の急斜面も視界に入り、さらに緊張感が増す。
なんとか仏岩の近くまで下りて、ようやく斜面が緩まり、落ち葉も減ったために歩きやすさが戻ってきた。
登りでは大変だと感じた序盤の急登も、下りでは安心感のある急坂に印象が変わっていた。
暖かな樹林帯は良い
登山口を示す看板まで下りてくると、林道の氷はすっかり溶けていた。
足元は泥濘んで、登山靴には泥が付く。
車で上ることができる程度の勾配で幅も広く、のんびりと歩けるように思えていたところで、日影に残る氷で足を滑らせた。
転ぶことはなかったものの、車で踏みしめられて固い地面では転びたくもなく、ここまで下りても気が抜けないのかと。
車道の凍結ほど転んで痛いものはない