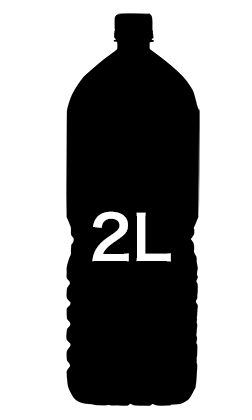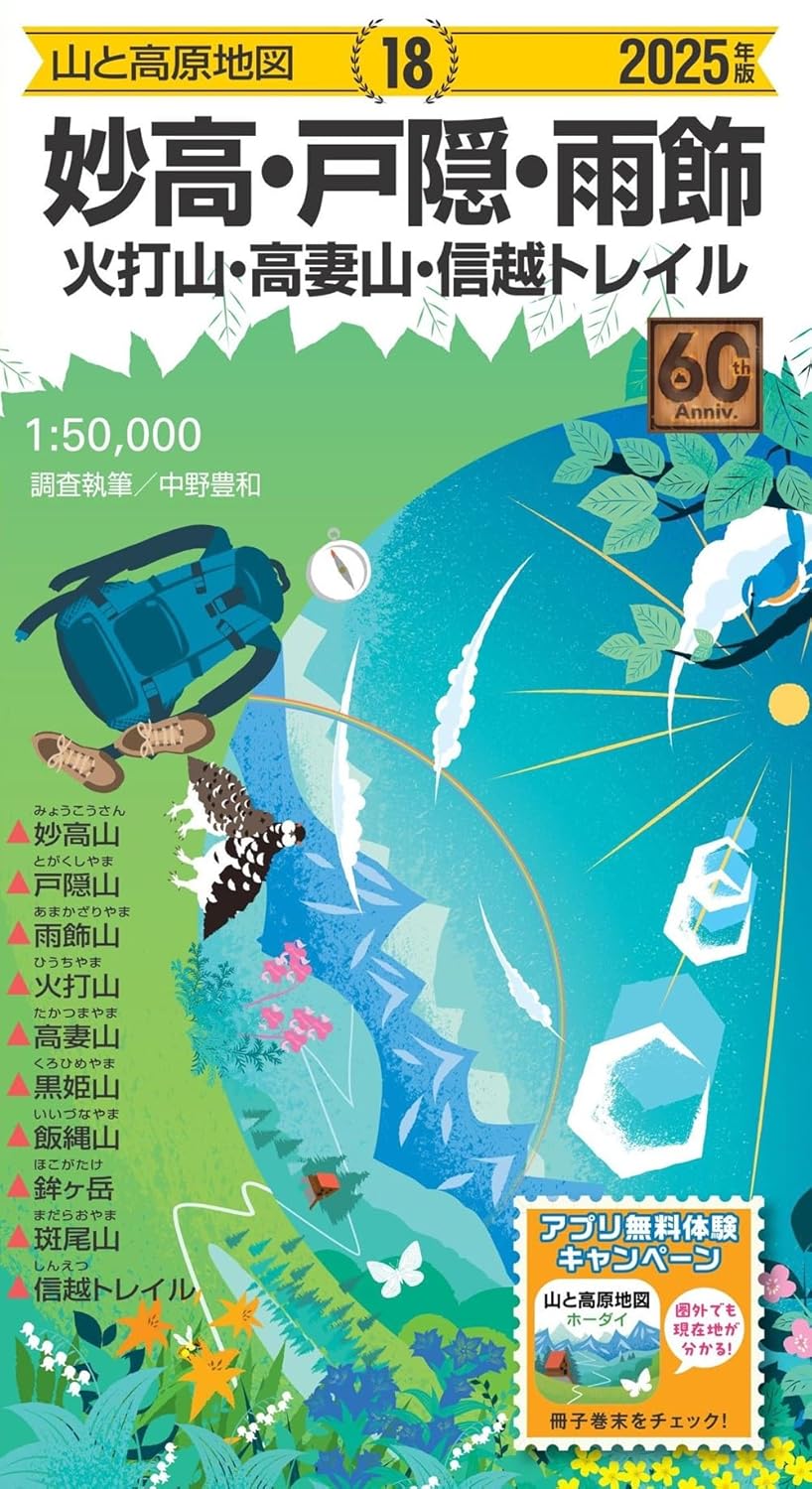戸隠キャンプ場から高妻山へ
まだ深く雪の残る戸隠から高妻山へと近づいていく。
戸隠へは上信越道長野ICから善光寺方面へ。
飯綱高原からバードラインを通って戸隠を北上していく。
積雪のある季節のため、夏季の駐車場は使えない。
戸隠キャンプ場の入口に車を停めて登山口へと向かう
登山口の戸隠キャンプ場はオープン前の準備と言ったところで、片付けられる前の雪と、片付けている最中で山積みになった雪とがあった。
夏に駐車場として使える広い敷地は、雪が積もっているために使える状態になるまでは時間が掛かりそうだ。
キャンプ場の入口にあるビジターセンターの横に車を停めさせてもらい高妻山へと向かう。
バンガローや雪の残っている敷地を縫うようにしてキャンプ場から戸隠牧場へ。
アスファルトの道路はきれいに除雪され、牧場に近づくと除雪された区間は終わり、道路には雪が高く残るように変わった。
標に沿って雪の上を歩いて行く。日中の暖かさで解けて朝晩に凍るのを繰り返した雪は、表面にだけ薄く氷が張り、踏みしめるとソール部分だけが埋まる程度に固まっていた。
牧場の奥まで緩い坂道を登ると、一不動と弥勒尾根新道との分岐点に出る。
夏季は一不動の登山道も使用できるが、雪の残る時季は一不動までに不安のある箇所があるため、弥勒尾根新道のある右へと進んでいく。
牧場を見渡すような緩やかな下り坂を弥勒尾根新道へ向けて進んで行くと、左側には五地蔵山、正面には黒姫山が見える。
牧場内の川を渡り、ふたたび緩やかに下り坂を進んで行くと登山口に到着した。
弥勒尾根新道を登る
登山口から入ってすぐに川を渡る。
雪解けで水量が増え、石を伝って歩くにも躊躇するような流れの速さ。
踏む石がぐらつかないことを確認しながら3mほどの川を渡り、雪の斜面へと入っていく。
序盤は木々がビッシリと繁った雪の斜面が続く。
テープは少なめでトレースも有るような無いような状態になっているが、尾根に沿って登っていけば良いルートなので、この付近では迷うような心配もいらない。
急斜面を登っては緩斜面に変わるという状態を繰り返して高度を上げて行く。
1時間ほど登ったところで、大きな杉の生えた尾根らしく丸みを帯びた登山道に変わった。
足元に大きな根が生えているせいか、雪は消えて落ち葉と土が露出している。
右側は崖のようになった雪の斜面、左側は崖とまではいかないものの雪の急斜面。
木の根に足を取られないようにしながら登っていく。
杉の根を過ぎるとすぐに急斜面になった。
夏はロープが張られている急勾配の登り坂で、雪の季節はロープは埋まってしまっているのでステップを切りながら急斜面をクリアする。
斜面を登り切って尾根上のピークに立つと、木の合間から五地蔵山が見えた。
ここからはまだ遠く、ピークから下りた鞍部が深く見える。
いったん下り再び急斜面を登っていく。
樹林帯に囲まれているので見晴らしは良くないが、徐々に見える景色が変わっていくのが分かる。
高く見えていた黒姫山は、いつの間にか視線と同じ高さにも見えてきた。
ピークから30分ほど登ったところで、身の回りを囲んでいた木々が減って見晴らしが良くなった。
改めて周りを見渡すと、黒姫山が大きく、飯縄山が視線と同じくらいの高さに見える。
戸隠牧場からは高く見えていた五地蔵山も目の前に見える。
足元は地面の笹藪が見えているところもあるが、1mほどは雪が残ってところどころでヒビ割れている。
五地蔵山直下の沢には雪が崩落した様子も見え、あまり近づきたくない雰囲気だった。
すぐ近くに見える五地蔵山は、なかなかに近づくことができず、斜面は急登に変わっていく一方。
一度の蹴り込みでは雪の斜面に十分なステップが作れず、2度蹴り込んで足場を固める。
バランスを崩せば沢へと滑り落ちそうな気にもなり、緊張しながら慎重に蹴り込んで登っていく。
稜線上の六弥勒には、登山口から2時間ほど掛かって到着した。
すぐ近くに五地蔵山のピークがある。
山影になって見えなかった高妻山も、ここに来てようやく姿が見える。
高妻山の大きな山容と、山頂の取り付きまで長く続く尾根のアップダウンを見渡し、五地蔵山までで良いのではないかという気持ちにもなった。
大きな存在感と近寄りがたい険しさが高妻山にはある。
稜線の登り返し
六弥勒をいったん下り、七薬師のあるピークへと登り返す。
ピークに立ったら七薬師の祠を横目に八観音への鞍部へと下りていく。
鞍部から八観音への登り返しは細い尾根道。
うねるように雪が残り、よじ登るような高さの雪壁になっていると思えば、解けて夏道が露出しているところも。
振り返るといつの間にか五地蔵山が遠く見える。
七薬師と八観音とそう長い距離を進んだわけでもない。
雪に埋まった八観音から九勢至までは八丁ダルミと呼ばれる尾根道が続く。
左右には木も少なく、風が冷たく吹き付ける。
遠く下に見える沢では交通事故のような音を立てて雪崩れている様子が見られた。
高妻山は近づくほどに険しさが増して見える。
九勢至を過ぎると尾根はますます細くなり、まるでナイフリッジのようにも見え、その先には壁のような急登が迫っている。
慎重に尾根を過ぎ、急登の取り付きまできたところでアイゼンを装着した。
高妻山山頂への取り付き
気温が高く緩んだ雪質ではアイゼンが効果的とも思えないが、前爪があることで蹴り込みが有効になることを期待して登る。
急登から見る景色は遮るものも無く絶景が広がっているはずで、ただ振り返って見渡す勇気が無く、体勢を変えた瞬間に滑り落ちるのでは無いかと思えて、ただ上へと目指して足を蹴り込んでいくことしかできなかった。
山頂の稜線が近くなってくると、雪が浅いのか笹や木の枝が露出しているところも。
細い枝にも手を伸ばして体を引き寄せるようにしてバランスを整える。
とにかく一歩一歩というつもりで登り、気が付くと稜線は近く、カウントダウンをしているかのように一歩ずつ急登を終えた。
稜線から山頂へ
緩やかに見えていた山頂への稜線も、その場に立ってみると意外と登りが見える。
十阿弥陀のある岩場も見えず、目指す先には雪の丘が見えるだけ。
端に寄りすぎないように注意をしながら稜線上を歩き、雪の丘を越えると十阿弥陀が見えた。
鏡のような形のモニュメントと祠に十阿弥陀と書かれている。
ここまでくると山頂はすぐのはずが、進む先にはそれらしきものは見えずさらに高い雪の丘が見える。
稜線に沿って雪の丘へと登りあたりを見渡すと、ここから先は下っているようだった。
高妻山山頂
なにもない小高い雪の丘に立っていると、足元に金属の板のような物を見つけた。
見覚えのある岩もあり、ここが山頂だということが分かった。
戸隠キャンプ場から歩き始めて3時間40分。
残雪期の高妻山に到着した。
雪が吹き付けるのか山頂部分だけ丘のように高く、もともと山頂が岩場だったことを考えると3mほどは残雪があるのではないかと見える。
乙妻山への登山道は、高妻山から一気に下るように続いている。
山頂からの景色は、南北を見渡すような北アルプスと、雨飾山と火打山、妙高山といった新潟と長野の境にある山々。
黒姫山と飯縄山、近くに戸隠山と西岳の険しい岩場が見える。
春の霞んだ景色で遠くまでは見渡すことができないが、うっすらと浅間山が見え、その右側には八ヶ岳も見えていたはず。
西側から吹き上げてくる風が冷たく、雪が丘のように盛り上がっているせいで身を寄せる場所も無く、風に当たりながら山頂の景色を楽しんだ。
高妻山からの下山
下山は登りと同じ弥勒尾根新道へ。
核心部の山頂直下の急登が要注意ポイントで、登るよりも下る方が格段に難易度が高い。
山頂で少し時間を過ごしたおかげで雪が緩み、強く蹴り込めば雪に足を差し込むことができるが、力の入れ具合でかえってバランスを崩しやすい。
下にある枝や木を見て、落ちた場合にどこで止まれるかを想像しながら、ゆっくりと急斜面を下りていく。
急登を下りて気持ちが緩んだところで、九勢至への登り返し、下ってからの八観音への登り返しが連続する。
八観音からは急な下り坂になり、七薬師への登り返し、六弥勒への登り返しとピークが連続していく。
なんとか六弥勒から弥勒尾根新道への分岐点に到着すると、真下には戸隠キャンプ場が見え、ようやく核心部を過ぎた安堵感を持つことができた。
緩んだ雪は膝に優しく、急登を下りるのにも都合が良かった。