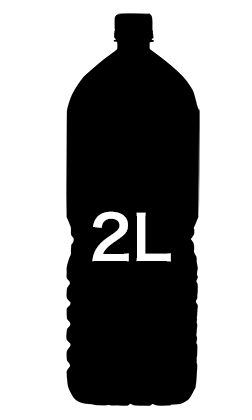紅葉の散る四阿山へ
登山口のゲートを潜ると、頭上には盛りを過ぎた紅葉が広がる。
牧場の真横を通るせいか、風が強く吹きつけ、木々の間を歩いている間も体が冷える。
足元の落ち葉を踏みながら緩やかに登り、5分ほどで登り坂は下りに変わった。
緩やかに下った後には緩やかに登り、小さな川を渡って登山道を進んで行く。
20分ほど歩き、車が通れそうな広さの登山道を左に折れるといよいよ本格的な登りが始まる。
中尾根へと登る
このルートは尾根を伝って四阿山へと登っていくようになっており、中盤に中尾根、小四阿といったピークが続く。
中盤からは眺めも良く、北アルプスを背負うようにして右手には浅間山、左手には根子岳を見ながら登っていく。
序盤は笹の葉が厚く茂った登山道を上っていく。
登山道を覆い尽くすような笹の葉の影には、5センチほどの霜柱が立ち、秋の終わりが近い雰囲気が感じられる。
中尾根への到着は登山口から40分ほど。
すでに左右が斜面になり、左右に景色が広がる。見上げる先には四阿山。その隣に根子岳が見える。
小四阿
中尾根を過ぎるといったん緩く下り、そこから徐々に登っていく。
5分ほどで四阿高原からの分岐に差し掛かった。
ここからも眺めがよく振り返って景色を楽しむ。
分岐を過ぎると足元には大きな石が目立ち始め、僅かながら急坂を登っていく。
するとすぐに岩のピークが見えた。このあたりも笹が薄く、景色を楽しむのにはちょうど良い。
再び緩く下り、四阿山山頂へと向かって急登が始まる。
おそらくこのルートでは小四阿と根子岳の分岐までの間がもっとも急勾配で、登りでも下りでも足の負担が大きい。
とはいえ、そう長く続く急座かではないのでガマンをしながら登り続けること15分ほど。
それまでの急坂がウソのように緩やかな登り坂に変わった。
その緩やかな樹林帯の先に視線を移すと、頭だけが飛び出るように四阿山の山頂が見える。
ここからの山頂はいつ見てもユニークだ。
山頂へ
四阿山の山頂が見えてから、いったん視界の利かない樹林帯に入る。ほどなくして根子岳との分岐があり、四阿山の方向へと足を進める。
とくに難しいところや危険な場所もなく、すぐ目の前に見える山頂を目指して登っていく。
山頂への取り付きは階段が整備されており、歩幅の合わない踏面に歩みを調整しながら登ると、すぐに四阿山に到着した。
登山口からは1時間44分だった。
四阿山山頂
四阿山の山頂は東西に細長く、ふたつの大きな祠が建っている。
そのうちの東側の祠が最高地点で、風を避けるためのような石壁が作られている。
山頂からの眺めは素晴らしく、新潟方面の山や、群馬の山、北アルプスと八ヶ岳、浅間山と富士山といった眺望を楽しむことができた。
ここまで来るとすぐ近くにみえる根子岳へ縦走し、菅平高原へと下りる欲が出てくる。
定番のコースでもあるので余裕があれば根子岳へも向かいたいところ。
今回は登りと下りを同じコースでピストンした。
登りでは凍っていた霜柱も、日中の陽の光ですっかり溶け、足元が悪くなっていた。登りよりも気を遣う土の状態だった。